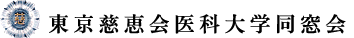東京慈恵医科大学同窓会
最新情報2024年08月25日 学祖の舞台が生まれるまで
熱帯医学講座担当教授 嘉糠洋陸
劇団主宰者である村田裕子さん(ライブアップカプセルズ)と私との縁は、細菌学黎明期の研究者・北里柴三郎に纏わる舞台「雷(いかづち)を振れり」を私が手伝ったことがきっかけである。赤痢菌を発見した志賀潔をはじめ、北里門下生とそれを取り巻く時代を見事に描き切ったシナリオを眺めながら、自分が決して相見えることの出来ない、百年以上前の過去の偉大な人物が、現在に生き生きと蘇る様子に驚愕した。もし、この村田さんが、学祖・高木兼寛を取り扱ったらどのように仕立てるのだろう、と思わず想像せずにはいられなかった。
その後、コロナ禍の最中に、村田さんから「高木先生の舞台を作りたい」との話が飛び込んできた。思わず、背筋が伸びた。本学と縁が深い渋沢栄一、鈴木商店の金子直吉、理研の仁科芳雄など、独自の目利きでテンプレート(鋳型)を選りすぐってきた村田さんが、幕末・明治時代の医史における傑物として、学祖に狙いを定めたのだ。
村田さんは、何はさておき、まずは高木兼寛のことを知りたいと言う。学祖を描いた作品といえば、吉村昭著の「白い航跡」(講談社文庫)の右に出る者はいない。しかし、これに依ってしまうことを、きっと村田さんは是としないだろう。そこで私は、生化学講座の第3代教授だった松田誠先生の「高木兼寛の医学」を、手持ちの全5巻、そのままそっくり村田さんに渡すことにした。学祖の正伝だけではなく、様々なエピソードも随所に織り込まれたこの書物は、私も随分と読み込んだものだ。松田先生が精魂込めて記述した学祖の有り様を、村田さんの脚本家としての卓越した手腕がどのように昇華させるのか、ある意味、私なりの仕掛けであった。
その後、作品の前提になる高木兼寛の人となりについて、全てにおいて前のめりの村田さんと、膝を突き合わせ、時に電話やメールで、何度も意見交換をした。その際に、私が繰り返しお願いしたことは、「縛られずに、学祖のことを自由に描くこと」であった(村田さんは、我々慈恵関係者が持つ、学祖のイメージを壊してしまうことを本気で心配していた)。本当に優れて魅力的な伝記物は、ノンフィクションやドキュメンタリーの要素だけでなく、知り得ない部分・文脈を想像して練り上げた、ひとつの創作としての性質を持ち合わせているものである。舞台も同じであり、今風に言えば「シン・高木兼寛」を、私自身が渇望したのかも知れない。
果たして、霧が掛かる埠頭で、汽笛の音とともに、旅行カバンと帽子を携えた高木兼寛が現れた。松田誠先生は、残念ながらこの舞台公演が始まる直前にご逝去された。もし観劇していたら、村田さんにどんな感想を述べただろうか。