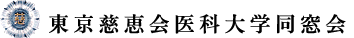東京慈恵医科大学同窓会
最新情報2024年08月25日 科学的能力とは何か?
劇評 村田裕子作・演出「須く、一歩進む」
臨床検査医学講座客員教授 加藤 茂孝
感銘深い作であった。これは、ビタミンが未解明だった明治期において、日本軍人に大きな被害をもたらした「脚気」の原因をめぐる歴史劇である。海軍軍医の高木兼寛と陸軍軍医の森林太郎(文学者としては鴎外)との学問的および組織的争いの緊迫した劇であった。
「脚気」という言葉が舞台上を飛び交っていた。しかし、劇が始まってすぐ、気が付いた。隠れた主役は、この5年間パンデミックが続いている新型コロナウイルス感染症であり、その対応に右往左往した社会を描き示し、あなたならどうしますか?と観客に迫っていた。
鴎外は、ドイツで、最先端の衛生学細菌学を学んで来たのに、現場を重視する疫学的な考えが乏しかったのではないかと思われる。一方の高木は、イギリスへ留学して、現場重視の伝統を学び、疫学的感覚が優れていたように見受けられる。
感染症学の歴史から見れば、病原体が分からなくとも、治療や予防などは疫学的観察から成し遂げられてきたことが多い。コレラ菌が見つかる前に、コレラ患者の分布の中心地帯にあるポンプによる感染拡大を疑い使用を禁じたスノーの慧眼、天然痘ウイルスは見つかっていなくとも種痘で天然痘を予防できる事を見つけたジェンナー、狂犬病ウイルスが見つかる前に狂犬病ワクチンを作って噛まれた後の発症死亡を予防したパスツールなど素晴らしい例がある。鴎外は、陸軍やドイツ医学や帝大医学部などの権威性に押しつぶされて、自由な思考が出来なくなっていたのだろうか?
高木が鴎外より優れた研究業績を上げているのに鴎外ほど一般日本人の中では有名でないのは、日本の科学ジャーナリズムの貧困さをあらわしているのではないかと思われる。高木が、もっと正当に評価される日が来ることを望んでやまない。
このように多岐に亘って思いを馳せさせた名作であった。短期間の上演でかつ少人数にしか見られていないことが残念である。この作品はもっと広く見られるべき作品である。